スウェーデンのインクルーシブ教育の歴史ダイジェスト版!

この投稿は、旧ブログのインクルーシブ教育に関する投稿の中の歴史に関連した内容をまとめて、リライトして、再投稿しています。 2022年7月16日に、初の単著 「医療・福祉・教育・社会がつながるスウェーデンの多様な学校~子どもの発達を支える多職種協働システム」 を刊行。是非ご一読を😊 今日は、「 本で知ることができない、スウェーデンのインクルーシブ教育とは 2017年版 」 「 発達と学ぶ権利を守る、スウェーデンの特別支援学校とインクルーシブ教育 」に続き、「スウェーデンのインクルーシブ教育の歴史ダイジェスト版」を、旧ブログの投稿をリライトしながらご紹介していきます。 1.1968年、全ての子どもに教育を受ける機会が与えらる 世界でも有数の福祉国家スウェーデンでも、障害がある子どもや大人の権利獲得は、常に戦いの道のりでした。日本と同様に、学ぶ権利をはく奪された時代は長く、「馬鹿者」と呼ばれて、生まれると施設に預けらえていた時代もありました。そんなスウェーデンの歴史の中で重要とされるのが、1968年。この年に、やっと、すべての子どもに教育を受ける機会が与えられました。日本より11年早く制度化されましたが、この時点では、私の生徒たちの教育は、社会庁の管轄で、ほかの学校と同様に学校庁の管轄になったのは、1990年代になってからです。この歴史により、スウェーデンの特別支援学校は長らく医療や福祉の分野が強く、教育や特別支援教育色が薄いところがあったのですが、ここ10年で大きく変わったと思います。 2.インテグレーション「場の統合」 インクルーシブ教育が叫ばれるようになる前、ちょうど私が大学生だったころは、インテグレーションという「場の統合」が注目される時代でした。スウェーデンでは、上記の1968年以降、1970年代や80年代は、この場の統合が盛んにおこなわれ、ノーマライゼーションの動きとともに、スウェーデンは「大型施設」を廃止しました。現在のスウェーデンでは、ほかの国で見られるような障害者だけが集められた大きな施設は存在しません。特別支援学校は、例外や民営の学校を除き、基礎学校と呼ばれる小中学校に併設する形になっており、支援学校の組織は、学校全体の1割以下が望ましいといわれています。これらは法制度されているものではないので、国内に支援学校単体で立っているものももちろんありま...

.png)
.png)

.png)
.png)



.png)
.png)
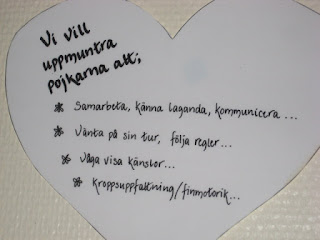

.png)
.png)